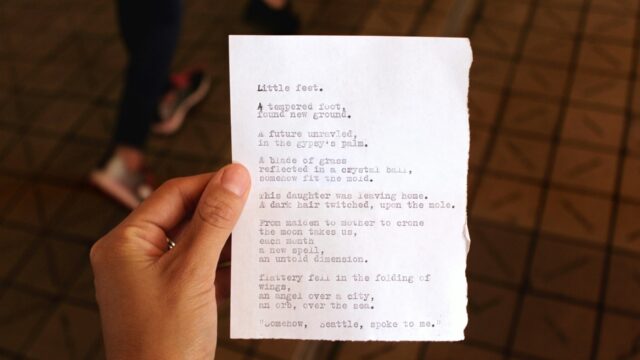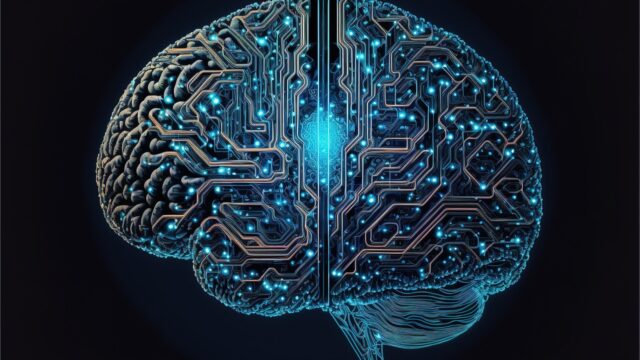─ YouTube「The King of Learning Tools (FULL GUIDE + SETUP)」完全解説レビュー
本記事では、Obsidian活用で注目を集めるYouTuber Odysseas 氏による動画「Obsidian: The King of Learning Tools」の内容を詳しく解説します。
この動画は、Zettelkastenをベースにしたノート術と、その実践方法をObsidian上でどう構築するかを、フォルダ設計・テンプレート・思考の深め方まで丁寧に紹介した、約36分の実践ガイドです。
初心者にもわかりやすく、Obsidianを“学びの装置”として最大限に活かすための知見が詰まっています。
🎥 紹介動画:
作者:Odysseas氏
🔰 はじめに – 「完璧なノート」を目指すのはやめよう
動画冒頭では、ノートを始めるときに多くの人が陥る“完璧主義”の罠が語られます。
「完璧なフォルダ構成」「理想のタグ付け」「一貫したテンプレート」……
最初からそれを目指すのではなく、
“まずは雑でもいいから書き出すこと”
“使いながら自分仕様に進化させていくこと”
このスタンスこそが、長く使えるノート術の鍵だと説かれています。
1. 📚 Zettelkastenの価値とは?(02:59–09:14)
Zettelkasten(ツェッテルカステン)とは、ドイツ語で「カード箱」。
知識を「断片=Zettel」として書き出し、リンクでつなげることで、記憶と創造を促進する思考術です。
Zettelkastenは、情報を断片化し、それらをリンクで結びつけることで、知識のネットワークを構築する手法です。この方法は、情報を単に蓄積するのではなく、相互に関連付けることで新たな洞察を生み出すことを目的としています。ノートは単なる記録ではなく、思考を深め、創造性を引き出すためのツールとなります。Zettelkastenを活用することで、情報の整理が容易になり、アイデアの発展が促進されます。特に、Obsidianのようなツールを用いることで、デジタル環境での効率的なノート管理が可能となり、知識の有機的な成長をサポートします。
Zettelkastenがもたらす5つの価値:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 🔁 再表現 | 情報を自分の言葉で書き直すことで記憶が定着 |
| 🧠 思考補助 | ノートが「考えるための相棒」になる |
| 💡 創造性 | ノート同士のつながりから新しいアイデアが生まれる |
| 🧱 書く力 | 書きながら考える習慣が育つ |
| ⚒ 継続性 | 小さく・細かく・日常的に運用しやすい |
たとえるなら、「読書感想文」ではなく「思考のレゴブロック」。
Zettelkastenは、知識を貯めるのではなく、つなげて育てるという発想です。
2. 🗂 Obsidianの基本構成(13:30–22:30)
Zettelkasten的ノートをObsidianで運用するための、フォルダ・タグ・テンプレート設計が紹介されています。
なお、動画内ではフォルダやタグの運用についても独自の哲学が語られています。
彼の基本方針は非常にシンプルで、「最小限で柔軟に。使いながら育てていく」という考え方に基づいています。
フォルダは、ラフノート・情報源・メインノートなど、役割に応じた大まかな分類だけにとどめることで、ノートの書き出しを妨げない設計に。細かく分けすぎると、どこに書けばいいか迷ってしまうため、あえてゆるく保つのがポイントです。
一方、タグは検索性と関係づけを補うツールとして使用されます。分野やトピック、進捗状況(例:#draft、#to-review)といった機能的な視点からタグを絞って使うことで、複雑化を防ぎつつも効果的にノートを管理しています。
このように、「完璧な構造」を目指すよりも、「今すぐ書ける環境」を優先する姿勢が、Obsidianを日常に根づかせる鍵となっているのです。
🔹 フォルダ構成(例):
| フォルダ名 | 内容 |
|---|---|
Rough Notes | 思いつき・走り書き用のラフなメモ |
Source Material | 本・記事・動画などの情報源ノート |
Main Notes | 自分の考えを再構成したアトミックノート群 |
Templates | よく使うノート形式をテンプレ化して保存 |
🏷 タグ設計のポイント:
- 役割タグ:
#idea、#quote、#draft - 分野タグ:
#哲学、#ビジネス - 進行タグ:
#to-review、#needs-linking
📄 テンプレート例(Zettelkasten Note):
タイトル(1アイデア)
- 🧠 要点:
- 📚 出典:
- 🔗 関連ノート:
- 🏷️ タグ:
🧩 フォルダで分類、タグで検索、テンプレで加速。これが継続の鍵です。
3. ✍️ 書き方の実践(24:03–35:38)
このパートでは「どう書くか」が具体的に紹介されています。
Zettelkastenにおいて大切なのは、以下の3ステップ:
✅ Step 1:まず書く(Rough Notesに放り込む)
- 思いつき・気づき・疑問など、雑でもOK。
- 情報をアウトプットしないと、記憶にもならない。
✅ Step 2:1ノート1アイデア(アトミック化)
- ノートのタイトル=そのノートの主張。
- 内容は定義・理由・例・出典など、簡潔に1アイデアだけ書く。
- 複数アイデアが出てきたら分割する。
✅ Step 3:リンク・出典・タグで構造化
例
タイトル:人は物語で記憶する
- 結論:記憶は物語構造の方が残りやすい。
- 理由:因果・感情・流れが記憶を強化する。
- 出典:[[記憶の心理学]]
- 関連:[[ストーリーと学習効率]]、[[感情と記憶の関係]]
- タグ:#記憶 #学習
🔗 ノートは単体で終わらせず、つなぐことが創造につながる。
4. 🛠 応用とカスタマイズ(21:40–36:26以降)
Obsidianをさらに快適に使いこなすための応用機能やカスタマイズの工夫も紹介されています。
公式のコアプラグインや、ユーザーコミュニティが開発した拡張プラグインを活用することで、テンプレートの自動挿入、ノートの一覧表示、進捗管理、カレンダー連携など、学習・創作を支える機能が大幅に拡張されます。
また、ショートカットキーやテーマのカスタマイズにより、自分にとって最もストレスの少ない書き心地を追求することも可能。さらに、クラウド同期やモバイル連携を使えば、場所やデバイスを問わずノートを育て続ける環境が整います。
自分の目的に合わせてObsidianを育てていく──それが、このツールを“学びの装置”として機能させる最大のポイントです。
🔧 コアプラグイン(公式内蔵)
| 名前 | 機能 |
|---|---|
| Templates | テンプレ挿入 |
| Daily Notes | 毎日の日記・思考記録 |
| Backlinks | ノートの被リンク表示 |
| Graph View | ノート間のつながりを可視化 |
🧠 おすすめコミュニティプラグイン
| プラグイン | 機能 |
|---|---|
| Dataview | ノートの一覧化・進捗管理 |
| Calendar | カレンダーUIで日付ノート操作 |
| QuickAdd | ノート作成の自動化 |
| Advanced Tables | 表の編集が簡単に |
| Periodic Notes | 週・月次ノートの管理支援 |
☁️ 同期とモバイル活用
- 有料:Obsidian Sync(安定・安全・履歴機能あり)
- 無料:Dropbox / iCloudなどを手動設定
- モバイルアプリ(iOS/Android)と連携すれば、どこでも書けるObsidian環境が完成
🎯 自分に合った運用を見つけよう
最後に、動画はこう締めくくります:
ノートは「記録のため」ではなく「思考を深めるため」にある。
Obsidianは、その人の目的によって運用方法が大きく変わります。
たとえば、読書管理をしたいなら、読書ノート専用のテンプレートを整えて、要点や引用、気づきを記録しやすくするのが効果的です。
創造力を高めたい場合は、アトミックノートを基本とし、ノート同士を積極的にリンクさせることで、知識のネットワークから新たな発想が生まれる仕組みをつくることが重要になります。
執筆を支援するために使いたい場合は、「#draft」などのタグで進行状況を管理し、Dataviewプラグインを使って草稿の一覧や進捗を自動で可視化する方法が有効です。
このように、Obsidianは目的に応じて姿を変える柔軟なツールであり、「何のためにノートをとるのか」という問いが設計の出発点になります。
✍️ おわりに:Obsidianは「学びの習慣装置」になる
この動画は単なるツール紹介ではありません。
「学びを続ける仕組みづくり」そのものを丁寧に教えてくれます。
Zettelkasten × Obsidian × 自分らしさ
この三位一体で、「学びが残る」「考えが深まる」ノート生活をはじめてみませんか?