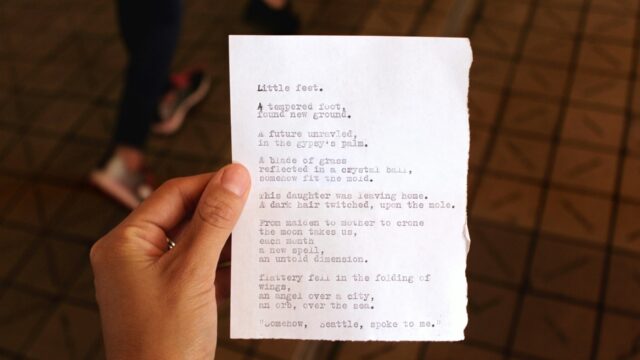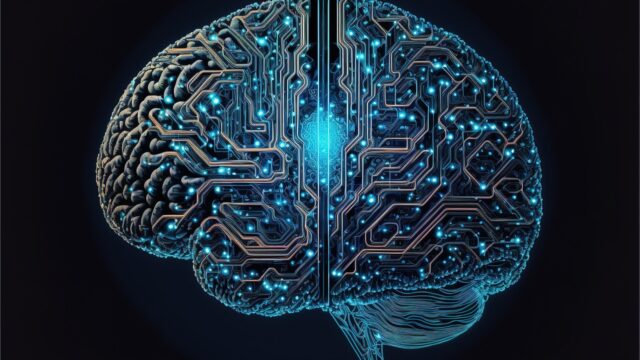2023年8月8日、知的生産ツール「Obsidian」の使い方を深く掘り下げたYouTube動画が公開されました。
投稿者は、ノートアプリを超えて“思考と学びの基盤”としてObsidianを使いこなすOdysseas Álvarez氏。
🎥 紹介動画:
作者:Odysseas氏
本記事では、動画の全貌を解説しそのエッセンスをお伝えします。
多くの人がノートアプリに求めるのは、“情報の整理”です。
しかし、Odysseas氏がこの動画で伝えているのは、それを超えた世界──
情報を“使い”、思考を“つなぎ”、知識を“育てる”ノート環境の構築です。
ここからは、フォルダ構造やタグ管理の徹底解剖に続いて、動画の全体構成に沿って各章を順番に解説していきます。
✅ 1. 完璧主義を避ける:Not Perfect, But Done
Odysseas氏は、動画の冒頭で最も強く訴えかけています。
「完璧を求めることが、あなたのアウトプットを止めている」
Obsidianのようなノートアプリに触れたとき、多くの人は「どの構造が最適か?」「どんなタグ体系が正解か?」と迷いがちです。しかし、その迷いこそが、“書くこと”そのものを妨げる最大の壁なのです。
✏️ 小さく始めて、試行錯誤しながら進める
- 最初は1枚のノートで十分
- 完璧な構造より「今書きたいこと」に集中
- 書きながら整理すればいい。Obsidianは「あとで直せる」環境
このように、Odysseas氏は“始めるハードル”を下げることで、知的生産を加速させるよう促しています。
🧠 2. Zettelkasten方式の紹介:リンクでつながる知識の森
Odysseas氏は、Obsidianの活用の中核に、Zettelkasten(ツェッテルカステン)の考え方を据えています。
これは、ドイツの社会学者ニクラス・ルーマンが開発したノート術で、「短く」「明確に」「つなげていく」ことを重視します。
🔗 Zettelkastenの3つの原則
- Atomicity(原子性):ノートは一つの考えにつき1枚
- Connectivity(連結性):ノート同士をリンクでつなげる
- Autonomy(自律性):どこから読んでも意味が通じる
📚 推奨書籍:「How to Take Smart Notes」
この手法を現代的に解釈・実践化したのが、Sönke Ahrensの著書『How to Take Smart Notes』。Odysseas氏はこの本を強く推薦しており、動画でも再三言及しています。
🛠 3. なぜ「遅くてもいい」:スロウワークという知的戦略
動画の中で彼が最も情熱を込めて語っているのがこの部分です。
「書くことは速さではなく、深さを求める営みだ」
Odysseas氏は、情報を“早く処理する”ことよりも、“丁寧に噛み砕き、自分の文脈に落とし込む”ことの重要性を語ります。これを彼はスロウワーク(Slow Work)と呼びます。
🧩 スロウワークの具体的なステップ
- 引用をそのまま保存せず、「自分の言葉」で再表現する
- ノートを読み返し、気づいた点を追記・修正する
- 関連するノートとリンクづけし、思考のネットワークを育てる
これにより、Obsidianはただの情報倉庫ではなく、思考を再構築する場へと進化します。
🔄 4. アイデアの再構築(リミックス)の力:ノートを“混ぜる”
ノートは「一度書いたら終わり」ではありません。むしろ、Odysseas氏はこう語ります。
「一度書いたノートを、あとから再構成することで、新しいアイデアが生まれる」
このプロセスは、ノートを“リミックス”することに他なりません。複数のノートを結びつけ、視点を変えて再解釈し、ひとつの新しいアウトプットへとつなげていきます。
🔃 実践例
- 2つの異なる読書ノートを見比べ、新しい仮説を導く
- 昔のアイデアノートに、今の考察を追記する
[[リンク]]を活用し、「違う文脈の交差点」を生む
✍️ 5. Obsidianをライティングアシスタントにする
Odysseas氏はObsidianを「書くための補助ツール」としても活用しています。これは単なるメモアプリの域を超えた発想です。
✍️ 実際の使い方:
- フォルダやタグで収集したノートをもとに、ブログ記事や論文の構成を組み立てる
#draftなどのタグで下書きノートを集め、進捗管理にも活用- Dataviewを使って「執筆中ノート」「仕上げ待ちノート」などを一覧化
このように、自分のノートがそのまま「一次資料」や「構成素材」として再利用できる仕組みが整っているのです。
🗂 6. 実践:フォルダ構造・タグ・テンプレート(※次の記事で解説)
ここでは、フォルダ・タグ・テンプレートの具体的な設計とその意図を解説しています。動画の中でも実践的に活用できる貴重な情報が紹介されていましたので、これだけでひとつの記事にしました。Obsidianの達人が語る「考えるノート術」──Odysseas氏が徹底解説するフォルダ設計とタグ管理
📝 ノート作成の流れ(35分頃〜)
動画の後半では、ノート作成の「実演」も紹介されています。ここでは、source note(資料ノート)→ permanent note(完成ノート)への変換ステップが示されました。
🪜 変換のステップ:
- 資料を読む(本・記事など)
- 引用や要約をとる(source noteに記録)
- 自分の文脈で再解釈(permanent noteへ転記)
- リンクとタグを付与(ネットワークへ編入)
この一連の流れにより、ただの情報が“使える知識”へと昇華されていくのです。
🧾 全体まとめ:Obsidianは「書くことのOS」になる
Odysseas氏が本動画を通じて伝えているのは、単なるノート術やツール紹介ではありません。
彼が提示しているのは、思考・学習・創造を支えるための「知的環境設計」です。
✨ 彼の実践から得られる3つの学び:
- 「とにかく始める」ことが最も重要な第一歩
- 「ノートは書いて終わりではない。再読・再構築して活かす」
- 「Obsidianは“思考の土台”となるパーソナルナレッジベース」
🗣 最後に:あなた自身の“考える場所”を育てていこう
ここまで読んでくださり、ありがとうございます。
Odysseas氏のノート術には、派手さやテクニックよりも、
「日々の思考を大切にする姿勢」が貫かれています。
ノートをとることは、ただ情報を整理することではありません。
自分の頭と対話すること、自分の未来と対話することです。
Obsidianは、そのための最高の“器”を与えてくれます。
でも、どんな形に整えるかは、あなた次第です。
🧭 まずは、完璧じゃなくてもいいから1枚のノートを書いてみる。
📌 少しずつ、自分に合ったフォルダやタグの形を見つけていく。
🔗 そして、気づいたらノート同士がつながり、思考が深くなっていく。
そんな「あなただけの知的空間」が、きっと未来の自分を支えてくれるはずです。
「思考の質は、ノートの質から育つ」
今日からあなたも、Obsidianとともに「考える力」を育てていきませんか?