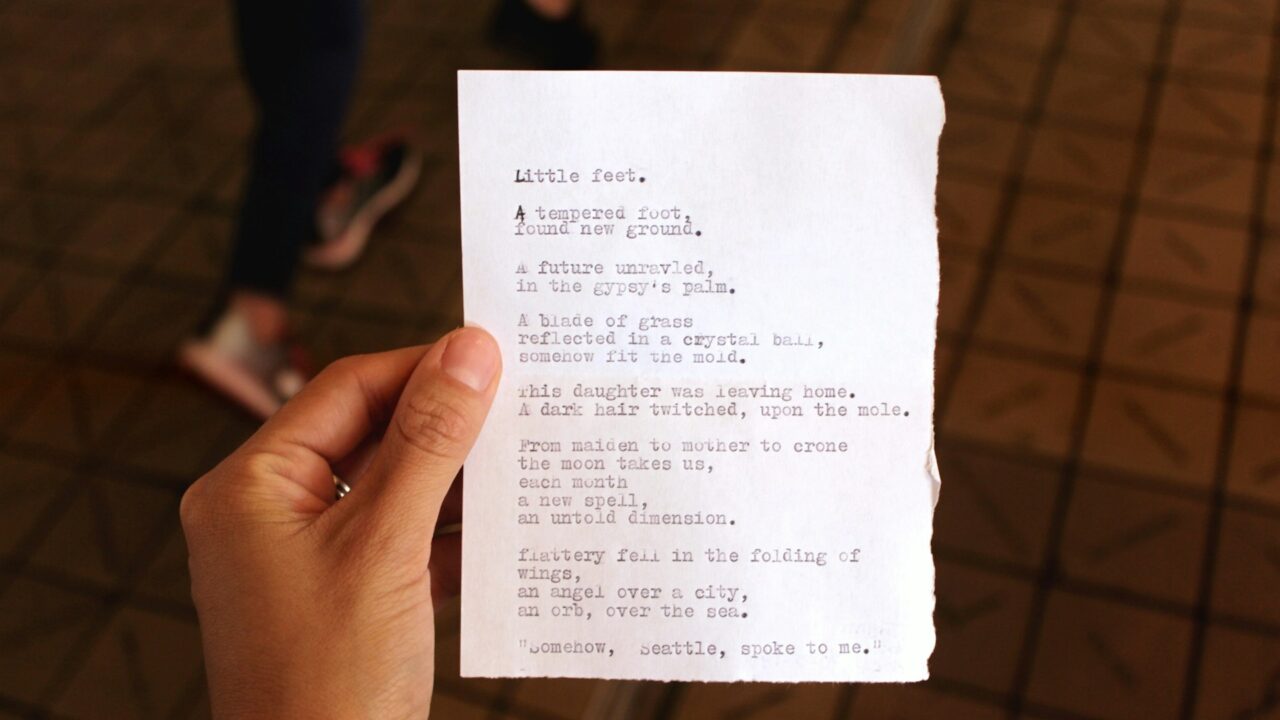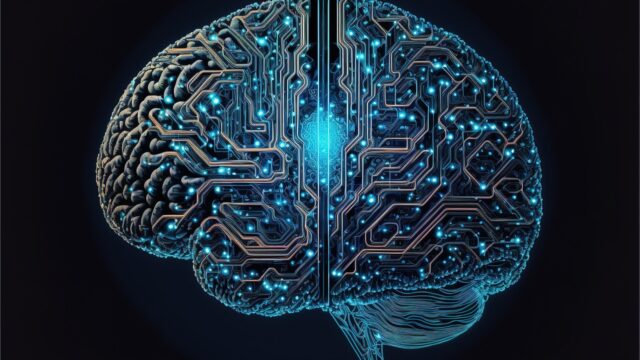2023年8月8日、知的生産ツール「Obsidian」の使い方を深く掘り下げたYouTube動画が公開されました。
投稿者は、ノートアプリを超えて“思考と学びの基盤”としてObsidianを使いこなすOdysseas Álvarez氏。
この生地は、前回の解説記事の後編となっており、フォルダ・タグ・テンプレートの具体的な設計とその意図にフォーカスして解説しています。
※前回の記事はこちらです。Obsidianは「情報の倉庫」ではなく「思考の器」 | Odysseas氏 「How to Become an Expert with Obsidian」を解説
🎥 紹介動画:
作者:Odysseas氏
本記事では、動画の中でも特に反響が大きかった次の2点を軸に、彼の知的ワークフローを徹底解説します。
- フォルダ構造:情報の流れと成熟を可視化する設計術
- タグ管理:ノートに“意味”を与え、つながりを育てる運用法
🧠 Odysseas流ノート術の核心
彼のスタンスはシンプルです。
「完璧に書こうとするな。まず書け」
「遅くていい。丁寧なノートが、深い理解と創造につながる」
この姿勢のもとに構築されたノート環境は、情報の蓄積にとどまらず、思考の循環と再利用を支える「知的な作業場」として機能しています。
🗂 Odysseas流フォルダ構造:思考の「流れ」を形にする設計
Obsidianにおけるフォルダ分けは、人によって大きく異なります。Odysseas氏の特徴は、思考のライフサイクルに沿った流れを設計している点です。
🔻 フォルダ構成の全体像
📂 00 Inbox
📂 01 Rough Notes
📂 02 Source Material
📂 03 Permanent Notes
📂 04 Projects
📂 Templates
これは見た目以上に“深い意味”をもった構成です。次の表で、各フォルダの意図を丁寧に解説します。
📁 各フォルダの役割と目的
| フォルダ名 | 用途・目的 | 内容例・使い方 | 効果 |
|---|---|---|---|
00 Inbox | 思いついたことを即座にキャプチャする仮置き場。「まず書く」習慣を支援 | タスクのメモ、アイデアの断片、リンクだけ貼ったものなど | キャプチャの心理的ハードルを下げ、行動力を最大化する |
01 Rough Notes | ラフに書き出したメモやアイデアを置いておく場所。未整理でもOK | インボックスから移動したメモ、まだリンクや要約が不十分なノート | 思考をアウトプットする習慣づけ。未完成でも保存できる安心感 |
02 Source Material | 書籍・Web記事・ポッドキャストなどからの引用や読書メモ。一次情報の吸収と記録 | 読書ノート、引用の整理、音声メディアの要約、講演メモなど | 情報を自分の言葉で再構成し、インプットを資産化できる |
03 Permanent Notes | 自分の言葉で再構築された完成ノート。Zettelkasten方式でアイデア同士をリンクさせる | 短く、明確な論点をもったノート。ほかのノートとのリンクが多数存在 | 思考のネットワークが構築され、新たな発見が生まれやすくなる |
04 Projects | 実務・学習・執筆など、目的をもった活動単位でノートを管理 | Project-A/Overview.md、Project-A/Meeting Notes/ など | 実行フェーズの情報を集約・追跡でき、作業効率とチーム連携が向上 |
Templates | テンプレートを保存して、ノート作成を高速化・標準化 | 読書ノートテンプレート、会議メモ、思考整理用テンプレなど | 一貫性を保ち、ノート作成を高速化。思考の枠組みを標準化できる |
🧩 プロジェクトフォルダの構造(例)
Odysseas氏は、プロジェクトを単なるタグや1枚ノートではなく、小さなワークスペースとして扱います。実際の構成は以下のようになります:
Projects/
├── Project-A/
│ ├── 00 Overview.md
│ ├── 01 Meeting Notes/
│ ├── 02 Tasks.md
│ └── Assets/
このように情報を分けることで、会議ログ・ToDo・資料・成果物が視覚的にも機能的にも整理され、プロジェクトの推進力が高まります。
🏷 タグ管理:ノートに「意味」を与える横断的ラベリングの設計
Odysseas氏が重視するのは、「タグは分類記号ではなく、“意味づけ”のためのラベルである」という考え方です。タグによって、ノート同士を構造の外側で横断的につなげることが可能になります。
🎯 タグ設計の基本原則
| 原則 | 説明 |
|---|---|
| 1. 内容ベースで付ける | ノートの内容や役割に基づいてタグを決定。フォルダと重複しないように運用 |
| 2. 数を絞る(乱用しない) | タグは1〜2個に抑え、運用の複雑さを回避。意味が似たタグは統合する |
| 3. 階層タグで整理する | #project/abc のように、プロジェクトやテーマで階層的に整理する |
🔖 代表的なタグとその意味・効果
| タグ | 用途・意味 | 効果 |
|---|---|---|
#quote | 引用が含まれるノート | 引用ノートを簡単に検索・一覧化できる |
#idea | 自分の思考・アイデアの断片 | 思考ログを時系列で振り返れる。発想の育成に役立つ |
#literature-note | 資料ベースのノート(書籍やWeb記事からの要約など) | インプットの整理に役立ち、出典管理もしやすくなる |
#permanent-note | 自分の言葉で書いた完成ノート | Zettelkasten的な知識ネットワークの構築が可能 |
#project/abc | 特定のプロジェクトに関するノート | Dataview等でプロジェクトごとに自動一覧化できる |
#child | 子育て・教育など、個人的テーマに関連するノート | プライベートな関心領域の分類と発想整理に役立つ |
🧠 タグの応用とDataview連携
タグを活かすことで、目的別・属性別のビューが作成可能になります。以下はDataviewの実例です:
table file.mtime as "Last Modified"
from #project/abc
sort file.mtime desc
これにより、#project/abc に関連するノートを自動で更新順に並べるビューが生成され、
フォルダ階層に依存せず、内容ベースで情報を引き出すことができるようになります。
📝 まとめ:Odysseas流 Obsidian運用のエッセンス
| 観点 | 目的 | 効果 |
|---|---|---|
| フォルダ設計 | 思考・情報の成熟プロセスを反映する | ノートが自然と「育つ」仕組みを構築できる |
| タグ設計 | ノートに意味を与え、再利用・連携を促す | 検索性・発想の横展開・ネットワーク構築が可能になる |
| 実務への応用 | プロジェクトや教育、執筆など多様な業務に柔軟に対応 | 情報が迷子にならず、行動に直結するノート環境が作れる |
💬 最後に:ノートとは「対話する思考空間」
Odysseas氏が繰り返し伝えていたメッセージは、次のようなものでした:
「ノートと対話しよう。早くまとめるより、深く考える方が大切だ」
完璧を求めて手が止まるより、まず書き、振り返り、つなげていく。
この「スロウワーク」の姿勢こそが、思考の質を高め、知的生産の原動力になるのだと、彼は静かに語ります。
☕ おわりに:あなたにとってのObsidianは?
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
この記事で紹介した内容は、Odysseas氏のノート術のほんの一部にすぎません。大切なのは「そのまま真似すること」ではなく、自分に合った形にアレンジしていくことだと思います。
Obsidianは、どんな仕事にも、どんなライフスタイルにも寄り添える柔軟なツールです。だからこそ、“正解のない自分だけの使い方”を育てていけるのが、このアプリの面白さでもあります。
あなたもぜひ、今日から一つのノートをつくってみてください。
完璧じゃなくて大丈夫。リンクもタグもあとでいい。
書いて、見返して、また書き足して。
そうやって積み重ねたノートは、きっと未来のあなたの味方になってくれるはずです。
「ノートとは、自分との静かな対話」
Obsidianというツールの先に、あなたらしい思考の空間が広がっていくことを願っています。